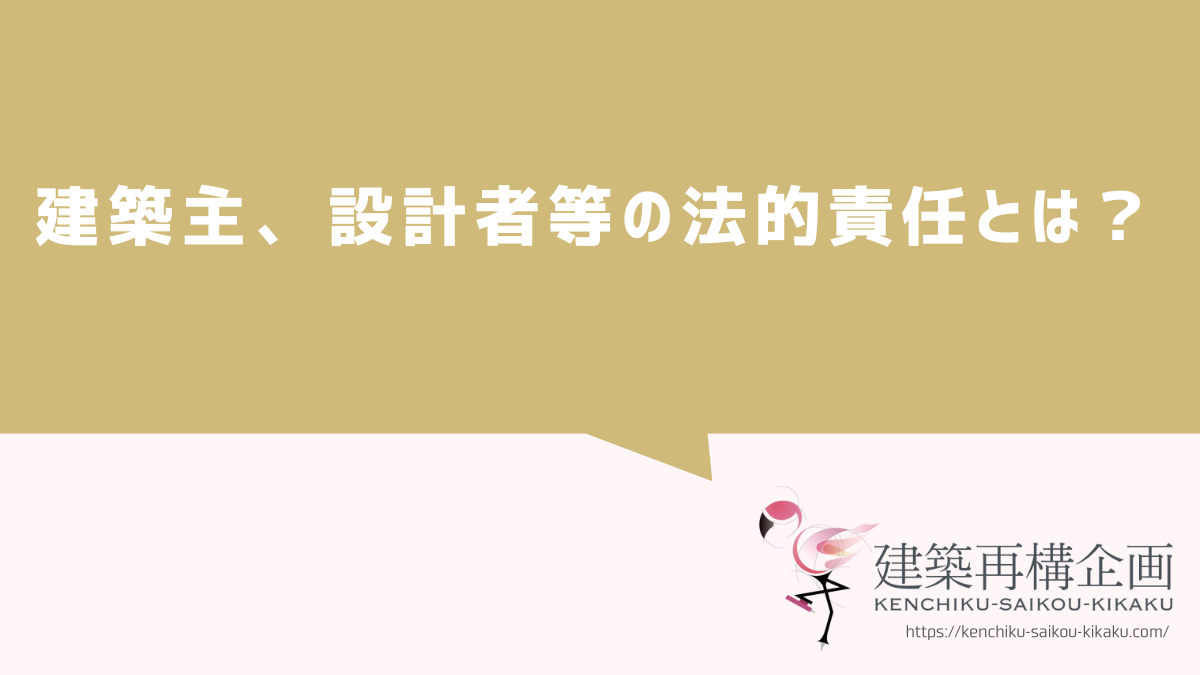
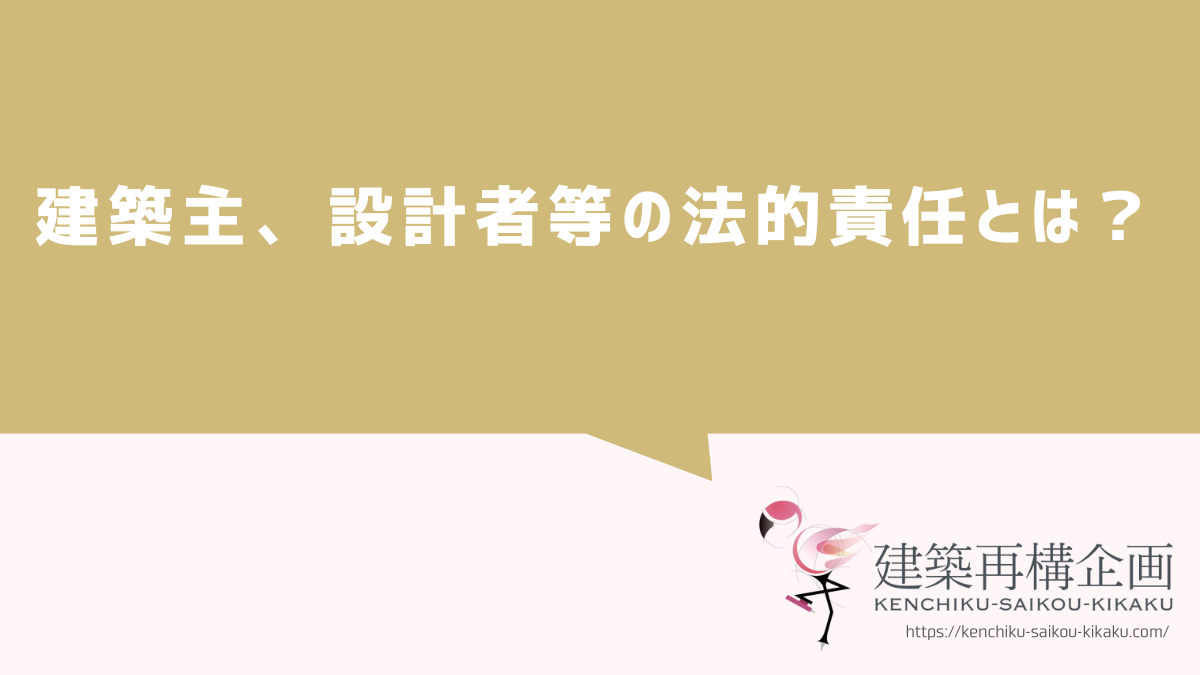
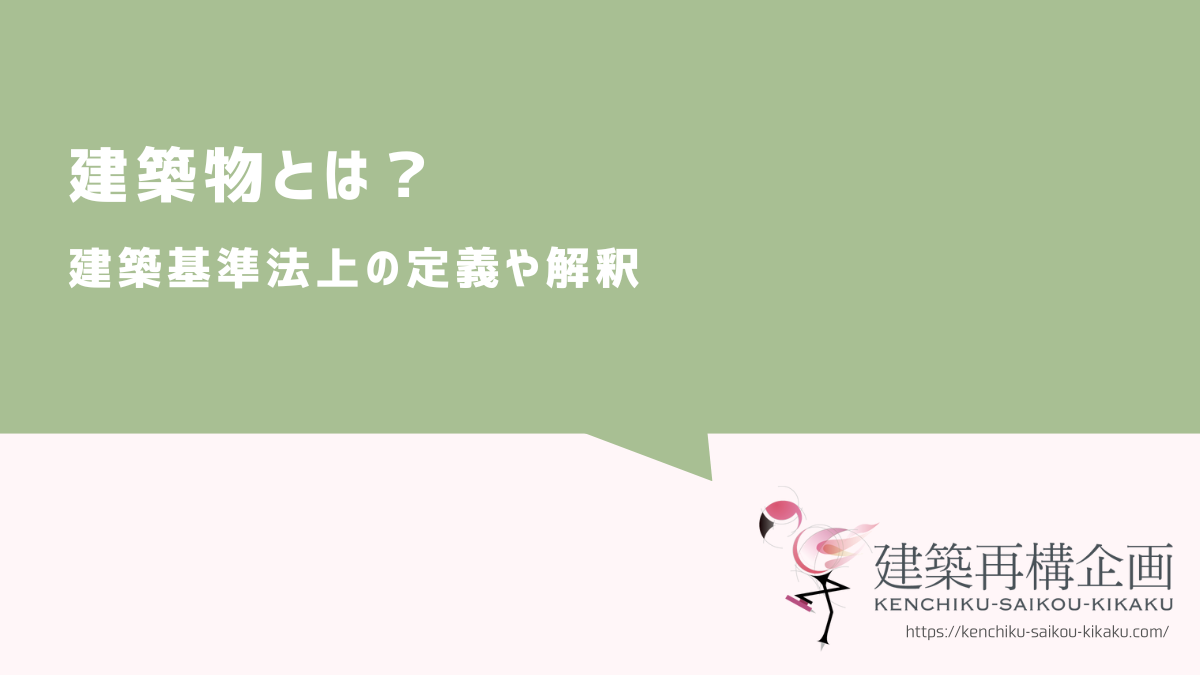
建築物とは?建築基準法上の定義や解釈
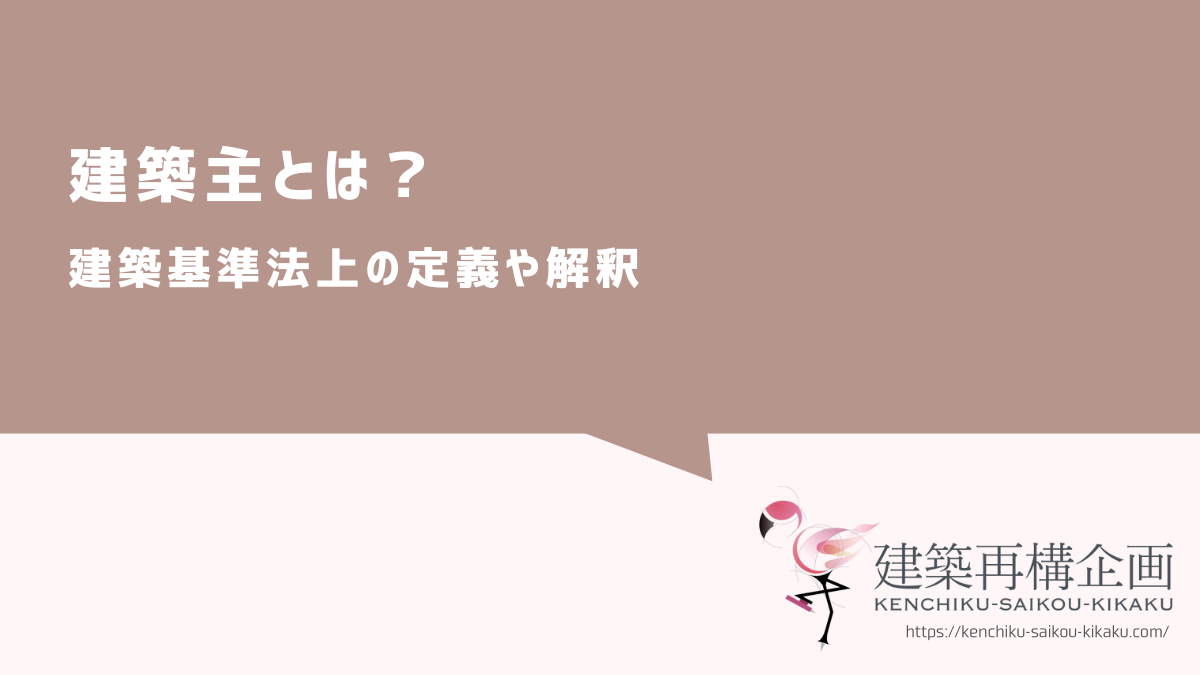
建築主とは?建築基準法上の定義や解釈
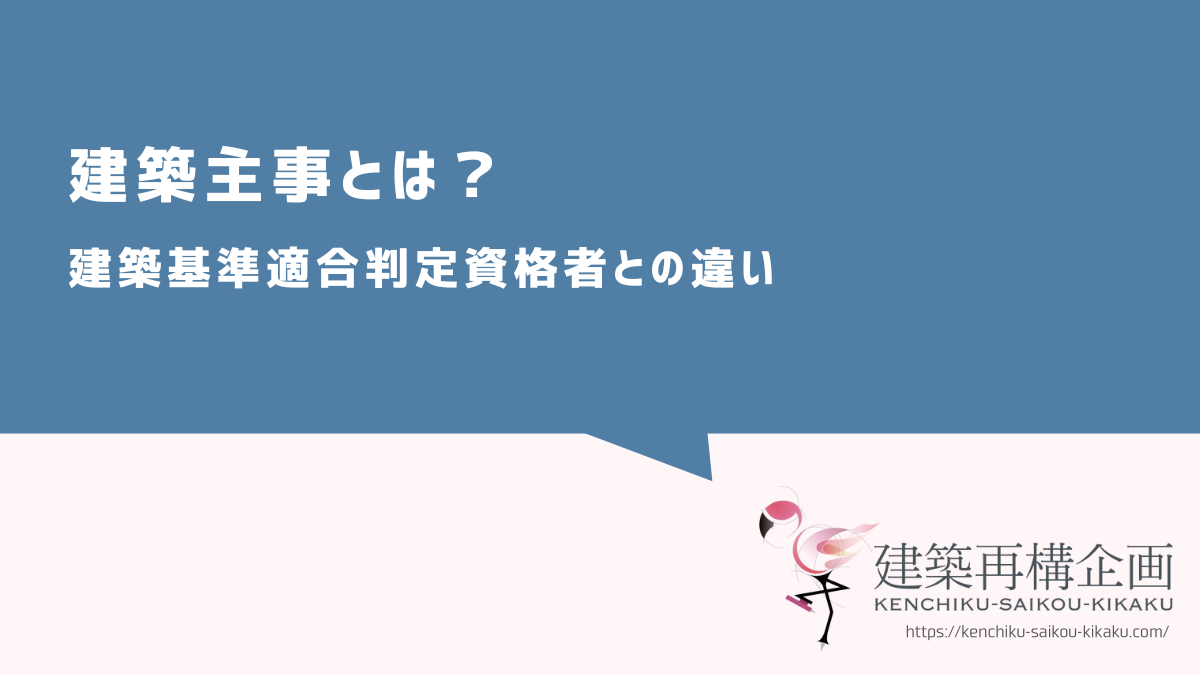
建築主事とは?建築基準適合判定資格者との違い
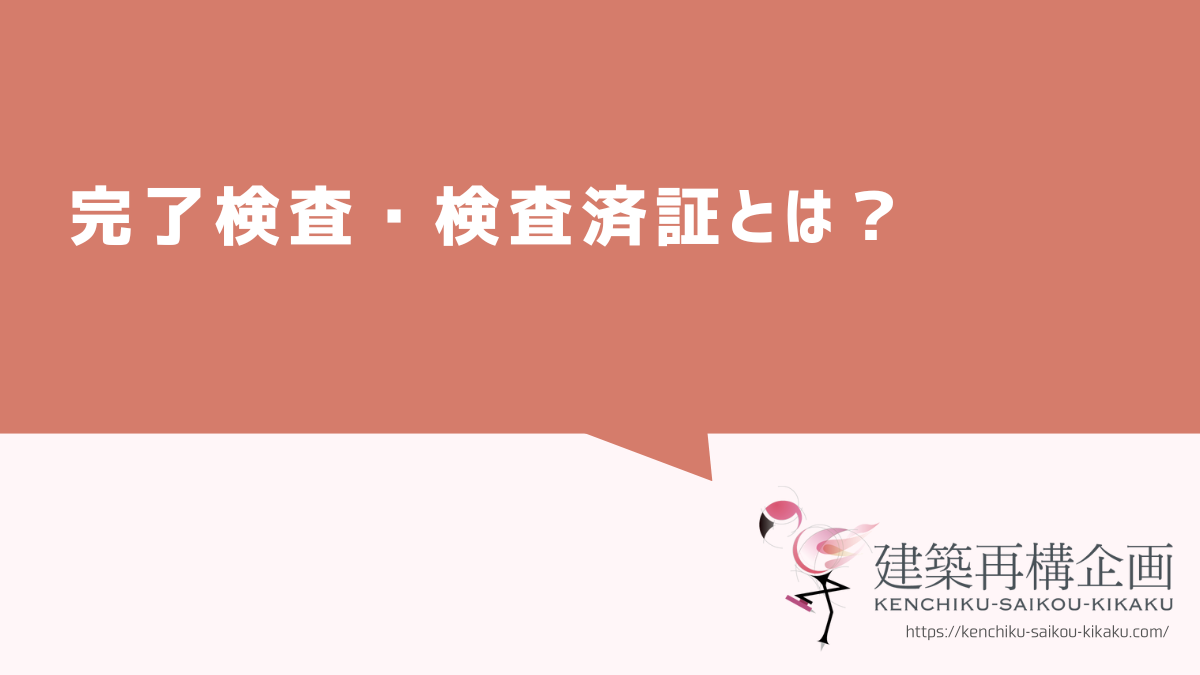
完了検査・検査済証とは?

東京建築士会開催のセミナー「既存不適格緩和の扱い方」にて遡及適用に関する法文や実例を解説しました
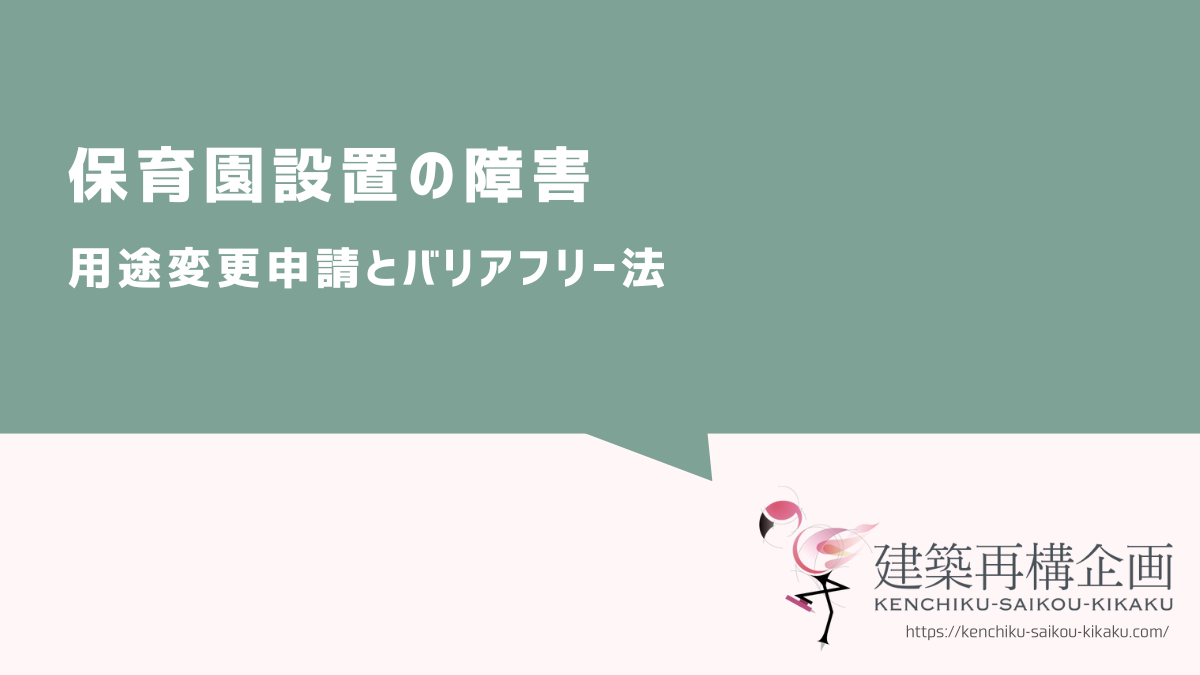
保育園設置の障害:用途変更申請とバリアフリー法

SYNQAブックセレクション:「意外と身近な建築基準法とその関連法規」

既存不適格建築物とは?(4) -既存不適格の範囲3:令137条の13、14-
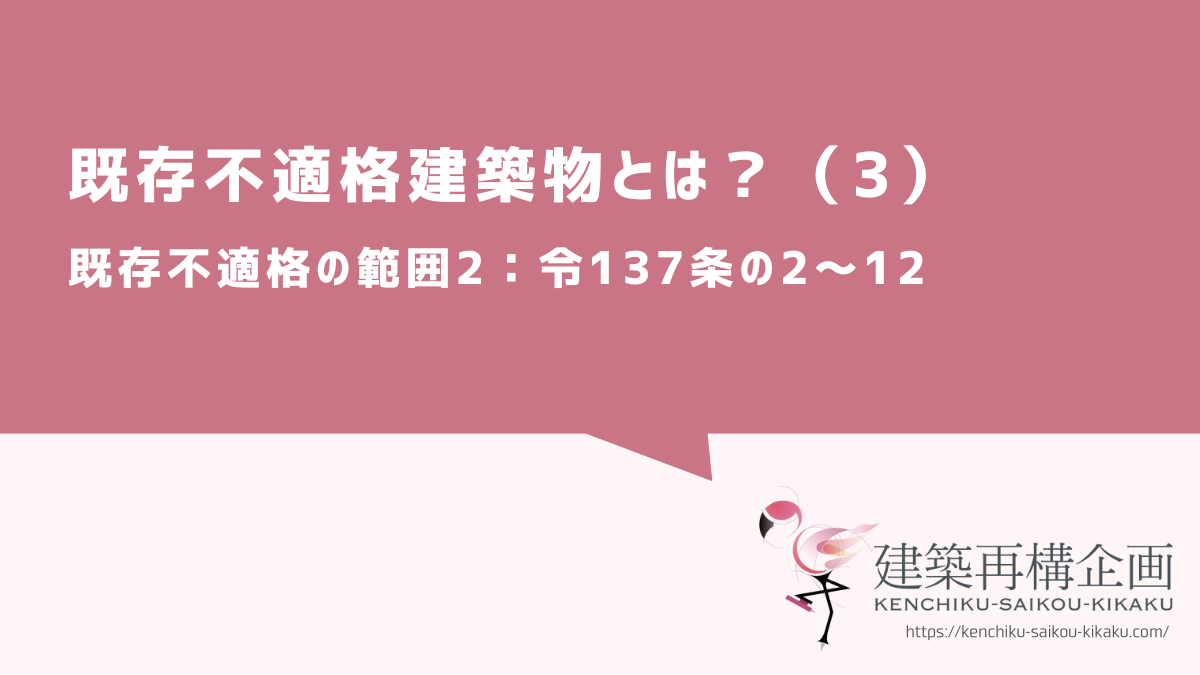
既存不適格建築物とは?(3) -既存不適格の範囲2:令137条の2~12-
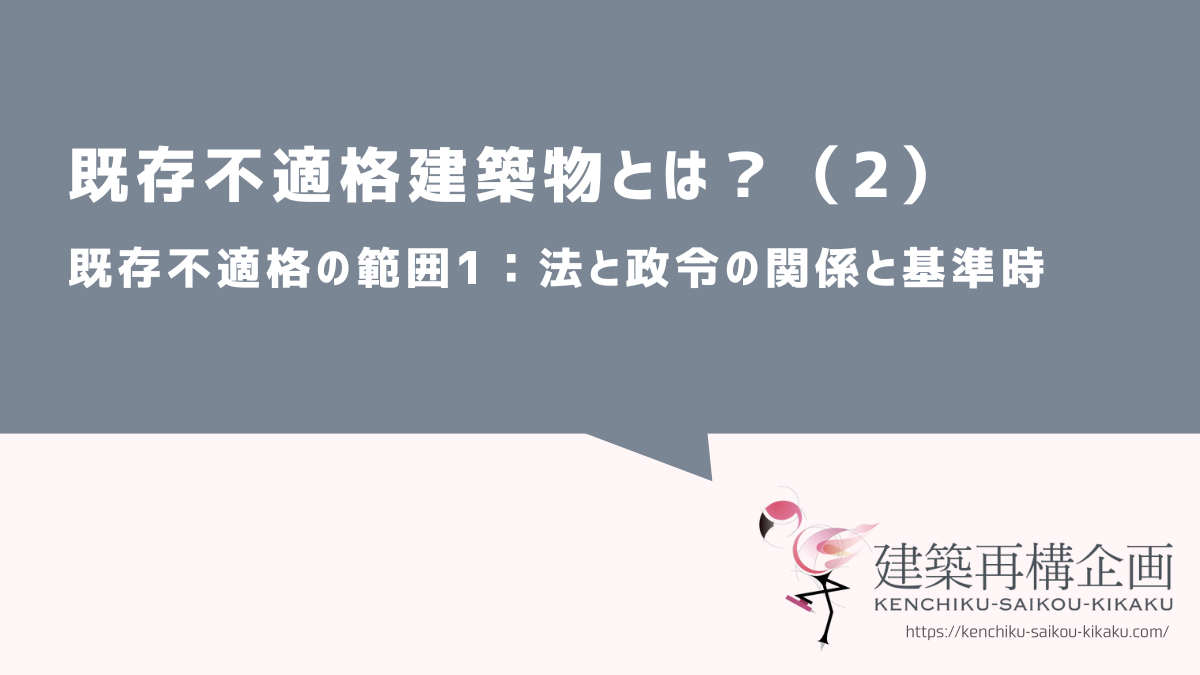
既存不適格建築物とは?(2) -既存不適格の範囲1:法と政令の関係と基準時-
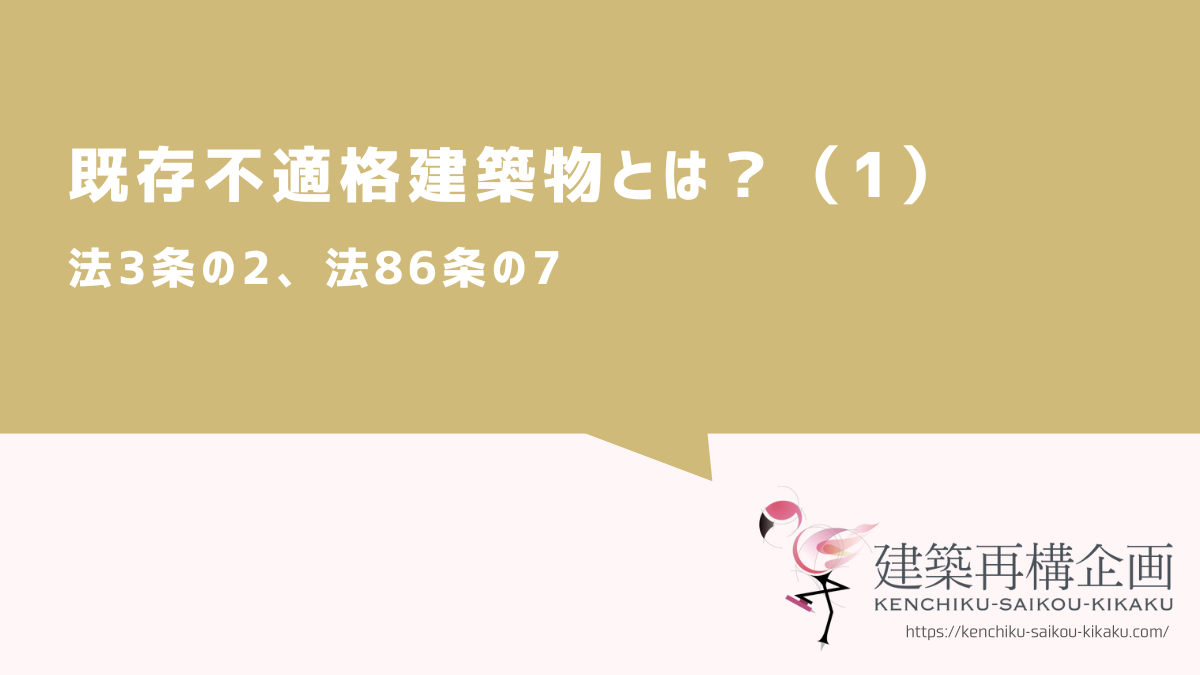
既存不適格建築物とは?(1)-法3条の2、法86条の7-
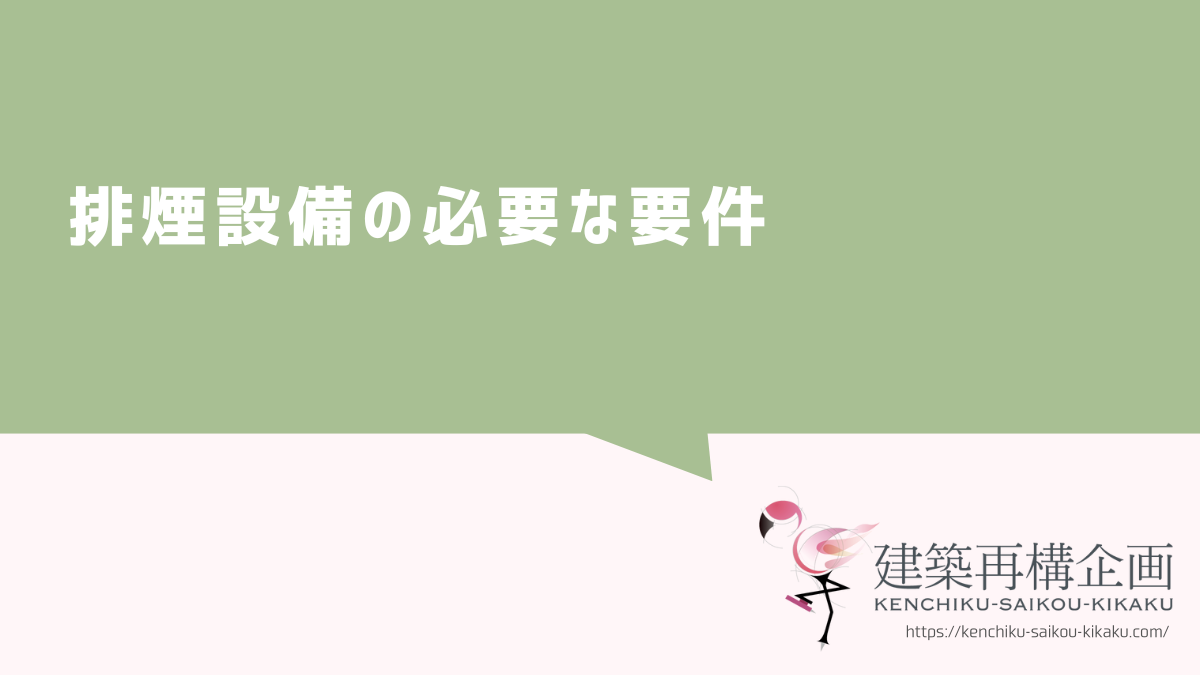
排煙設備の必要な要件
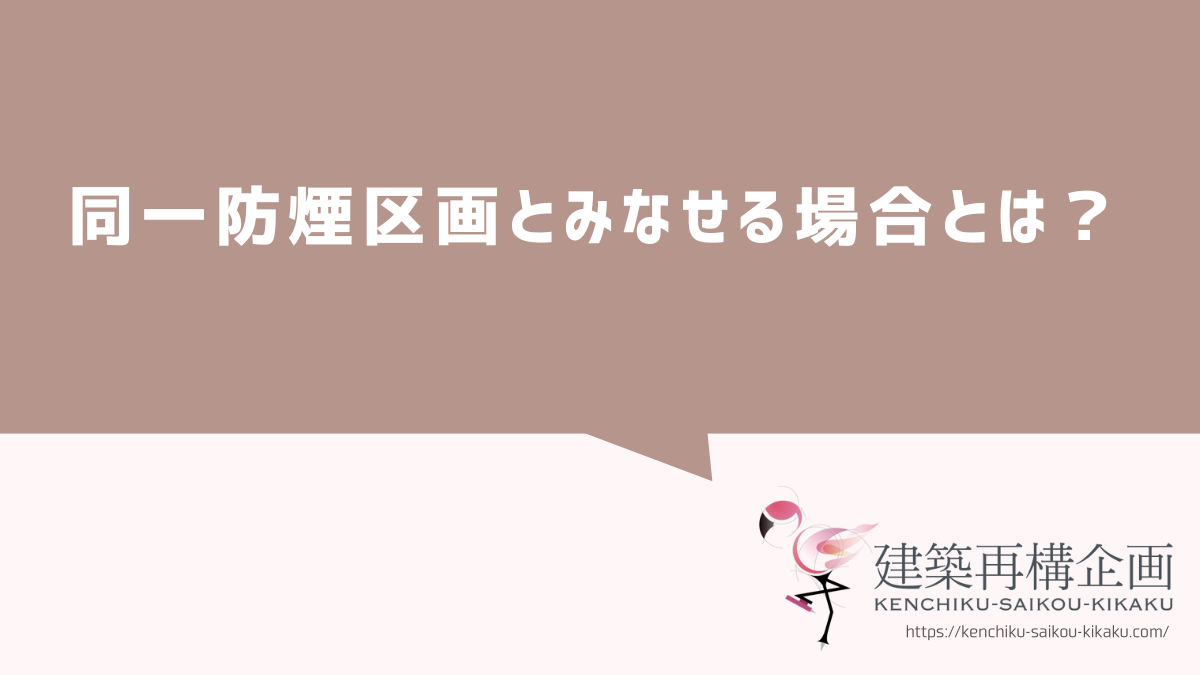
同一防煙区画とみなせる場合、みなせない場合

